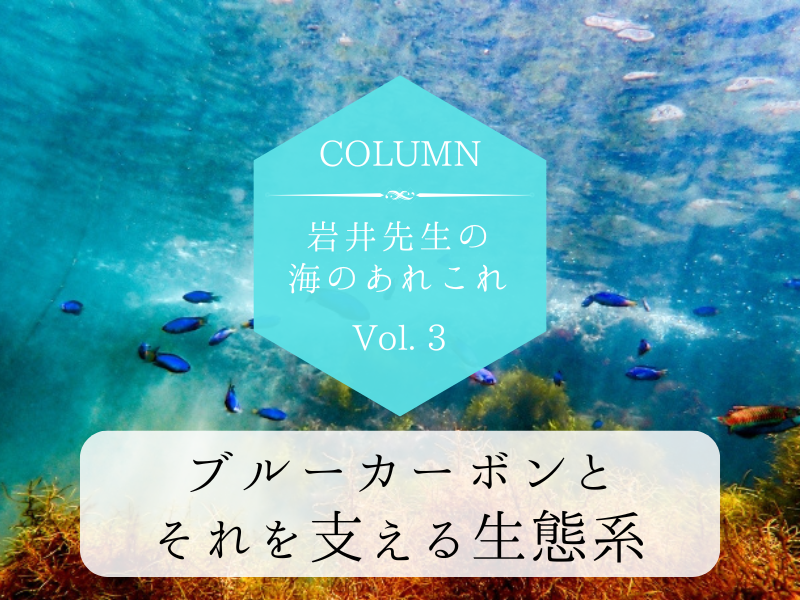
岩井先生の海のあれこれ Vol.3
ブルーカーボンとそれを支える生態系
ブルーカーボンとは、大気中の二酸化炭素や海水に溶け込んだ二酸化炭素が海岸のマングローブや干潟、塩性湿地、海中の海藻・海草などの生態系の光合成によって吸収され、地中や海底などに長期間貯蔵・固定された炭素です。
ブルーカーボンが重要なのは、大気中から二酸化炭素を吸収して貯蔵することによって、気候変動の影響を軽減する役割を果たすからです。

この数年、ブルーカーボンが経済界でも話題となっています。
日本テレビは「日本列島ブルーカーボンプロジェクト」を始動させ、メディアの重要な役割としてカーボンニュートラルの実現とその積極的な情報発信を行っています。
また、日本製鉄や商船三井など大手企業も藻場再生技術開発やアマモ場造成を始めました。
これらの取り組みは、企業が環境に配慮した事業活動を推進し、社会的責任を果たす一環として行われ、企業の持続可能性への取り組みを強化し、顧客やステークホルダーからの信頼を高めるのに役立っています。

ブルーカーボンは、マングローブや海藻などの生態系がもたらす炭素の固定であるため、マングローブや海藻が健全な状態で維持され、それを支える環境や他の生態系が健全に維持される必要があります。
つまり、多様な生態系が存在できる環境(生物多様性)がブルーカーボンを支えています。
環境省では、国立公園などの法的に保護されている区域以外でのブルーカーボンを含めた生物多様性が人々の保全活動によって維持されている区域を「自然共生サイト(OECM)」として認定する仕組みをつくり、保全活動する団体を支援しています。

岩井克巳(いわいかつみ)
・株式会社 漁師鮮度 代表取締役
・NPO法人 大阪湾沿岸域環境創造研究センター 専務理事
大学卒業後34年間、海域環境改善技術の調査・コンサルタントの仕事に携わる。
現在は、阪南市の小学校で子ども達への海洋教育を行う他、「海のゆりかご」とも呼ばれるアマモ場の再生など様々な海の環境保全活動に取り組む。
2017年より大阪府初の漁協直営のカキ小屋「波有手(ぼうで)のカキ」のオープンに協力し、カキ養殖を手掛ける。